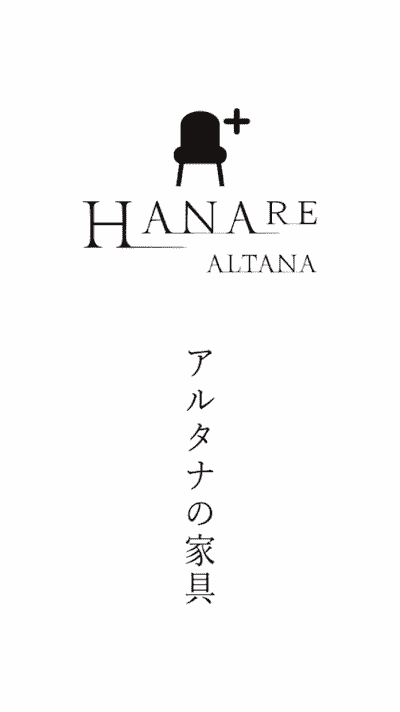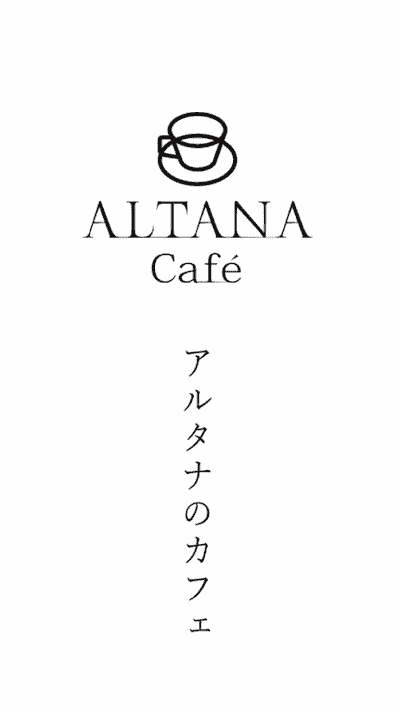お手本にしたい3人目は、随筆家・白洲正子。
白洲正子と言えば、骨董や古美術の目利きとして知られた存在です。
本物を見極める審美眼と教養を持つ女性像を思い浮かべます。
同じ誌面で連載が始まった、漫画家でコラムニストの辛酸なめ子のコラム「白洲なめ子を目指して」では、
憧れの対象として、正子になりきり、骨董の目利きに挑戦しています。
古美術店で「正子になったつもり」で器の裏側を見て高台をチェックする様子などは、シニカルですが…面白いです!
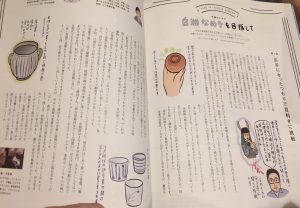
1901年、樺山伯爵家の次女として生まれた正子は、深窓の令嬢には納まらず、
4歳にして自らの意志で能を習い始め、14歳で女人禁制だった能舞台に女性として初めて立ったといいます。
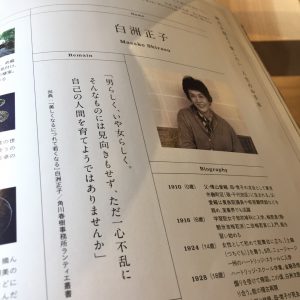
「韋駄天お正」のあだ名の通り、こうと決めたら、即行動の人。
未知の世界へ飛び込む時には一流の文化人に食らいついて、必至に知識と教養を身に付けていったそうです。
社会的地位を持つ家柄や夫・白洲次郎の経済力に守られながらも、その立場に甘んじず、生涯を通じて、
貪欲なチャレンジ精神を貫きました。

『花日記』は、そんな白洲正子の教養とセンスが詰まった「いけ花」の写真集。
形式に則った華道とは一線を画す、自身のコレクションの骨董の器に自邸の庭に咲く野の花を、思うがままに「いけて」います。
「花をいけるというのは、実にいい言葉だと思う。花は野にあっても生きているのに違いはないが、
人間が摘んで、器に入れ、部屋に飾った時、花は本当の生命を得る。
自然の花は、いってみればモデルか素材にすぎず、いけてはじめて「花に成る」のである。―『花をいける』より」
気取らず、さりげなく、花を取り入れる暮らしを愉しむヒントを教えてくれる一冊。
本書は、ALTANA Caféにございます。
ぜひ、お手に取りください。
響木図書館でレンタルも可能!スタッフまでお気軽にお声かけください。
本社・企画広報
山田 祐子